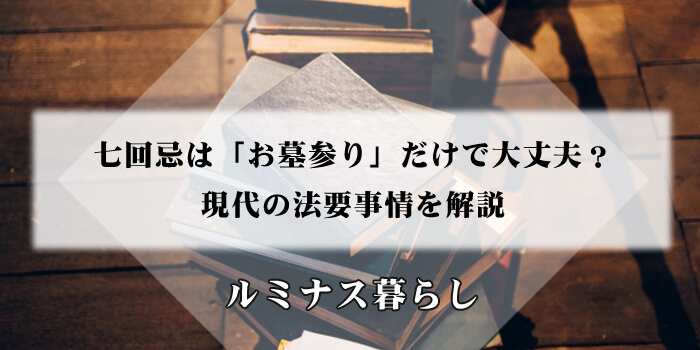「七回忌はお墓参りだけで大丈夫かな」「お坊さんを呼ばなくても問題ないの?」と迷っていませんか。
近年では、七回忌の法要を簡略化するご家庭が増えており、お墓参りだけで済ませる方も珍しくありません。ただ、親戚との関係やお寺との付き合いなど、判断に迷うポイントもあるのが現実です。
この記事では、「七回忌はお墓参りだけで大丈夫なのか?」という疑問に対して、一般的な考え方や注意点をわかりやすく解説します。
あわせて、お坊さんを呼ばないケースや自宅で供養する方法、費用の目安などもご紹介します。
後悔のない形で七回忌を迎えるために、ご自身の家庭に合った供養の仕方を一緒に見つけていきましょう。
七回忌 お墓参りだけで大丈夫なのか?
七回忌にはお坊さんを呼ばないのはどうですか?
結論からいうと、今の時代は特に問題とされないことが多いです。
昔は「お経を読んでもらわないといけない」みたいな空気ありました。でも今はそうでもないんですよね。
例えばですが、家族だけでお墓参りして、故人の好きだったお菓子を供えて、静かに手を合わせる。それで十分です。
今は核家族が多くて、
といった現実的な事情もあります。もちろん、お寺との付き合いがある場合は、一度相談しておくのがいいでしょう。
最終的に大事なのは、形式じゃなくて「どう偲ぶか」。ここさえブレなければ、自由でいいと思いますよ。
七回忌はやらなくてもいいですか?
七回忌は、必ずやらなければならない決まりではありません。
仏教的には意味のある法要ですが、最近は家庭の事情を優先する方が多いんですよね。
例えばですが、三回忌まではお坊さんを呼んでしっかり行って、その後はお墓参りや自宅で静かに手を合わせるだけ。これで十分というケースもよくあります。
今は家族が遠方に住んでいたり、高齢の方が多かったりして、集まること自体が大変だったりしますしね。
とはいえ、七回忌って気持ちの区切りになる節目でもあるんです。だから、形式より「どんな気持ちで偲ぶか」のほうが大切です。
「やらなくていい」と決めつけるより、「自分たちに合った形で偲べばいい」と捉えると気持ちが楽になりますよ。
七回忌が過ぎてしまった場合の対応
まず七回忌が過ぎていても、焦らなくて大丈夫です。そこまで厳密な決まりではありません。
うっかり忘れていたとしても、思い出したときに供養すれば問題ありません。大事なのは、気持ちの部分です。

例えばですが、都合のいい日に家族でお墓参りに行って、花やお供えをして手を合わせるでも、十分に供養になりますよ。
月命日に合わせて、改めて供養するのもおすすめです。
もし親戚に伝えるなら「少し遅れちゃいましたが、気持ちは変わらずです」と一言添えるだけで、トラブルになることもまずありません。
このあたり、昔よりもずっと柔軟です。誰かに怒られるような話でもないですしね。
供養って、形式よりも「心を込めて偲ぶ」ことが何よりも大切。思い出したそのときが、きっと一番良いタイミングなんだと思って大丈夫ですよ。
家族だけ自宅で七回忌を行う方法
七回忌を家族だけで、自宅で行うことは問題ありませんよ。最近はこのスタイルが主流だったりします。
まず日程ですが、亡くなった命日を基準に考えるのが基本です。ただ、平日だと集まりづらいこともありますよね。その場合は、土日とか、みんなの予定が合うタイミングで十分です。
次に準備についてですが、仏壇があればその前に以下を用意します。
仏壇がない場合でも、写真を飾ってテーブルの上にちょっとしたスペースをつくるだけでも気持ちは十分伝わりますよ。
僧侶を呼ぶかどうかは家庭によりますが、最近は読経を省略して、ご家族で静かに手を合わせるだけのご供養も多いです。
さらに、故人の思い出を話したり、好きだった曲を流したりすることで、自然と温かな空気になります。

注意点としては、香典や返礼品などのやり取りを省略する場合、親戚に一言伝えておくと後々のトラブルを防げます。
服装についても、略式の喪服や地味な色合いの服装なら問題ありません。
特別な形式にとらわれず、家族の気持ちを大切にしたやり方で進めていけば、それだけでも立派な七回忌になりますよ。
七回忌の法要を執り行う際の費用はどれくらいかかるか
ざっくり言うと、数万円〜十数万円くらいが一般的です。
状況によって大きく異なりますが、以下のような項目と金額が考えられます。
実際の例では、14名参加の七回忌法要で、施主の負担額が約16万8,000円という報告があります。(参考元:SOBANIより)
もし費用が気になるなら、お墓参りだけとか、家族だけで簡単に供養するスタイルも珍しくありません。無理のない範囲で、できる形を選べば大丈夫ですよ。
七回忌 お墓参りだけで大丈夫?他法要との違い
七回忌はなぜ重要なのか?
七回忌が大切にされているのは、仏教の考え方が関係しています。
七という数字には特別な意味があって、成仏や極楽往生の節目とされているんです。
この時期って、遺族にとっても気持ちの区切りになりやすくて、少し落ち着いた頃だからこそ、改めて故人を思い出すいいタイミングでもあります。
家族で集まって思い出話をしたり、「あのときこんな風に笑ってたよね」なんて話すだけで供養になります。
もちろん、形式にとらわれなくていい時代なので、気持ちを込めて偲べるなら、その方法に決まりはありません。今の家族の形に合ったやり方で、心を込めて向き合えるといいですね。
三回忌の際、お墓参りだけで大丈夫ですか?
答えは、状況によりますね。
お墓参りだけで済ませるご家庭も増えていますが、三回忌は一周忌の次に大事な節目と考える人も多いです。できれば法要も視野に入れておくと安心ですね。
例えばですが、僧侶は呼ばずに家族だけで手を合わせたり、仏壇にお供えして静かに過ごすケースも今では珍しくありません。

もし時間や人数の都合で法要が難しい場合は、命日やその前後にお墓参りをして、手を合わせることをおすすめします。
さらに、みんなで集まって食事をしながら思い出を話すだけでも、自然と気持ちは伝わりますよ。
ただし、お寺との付き合いがある場合は、一度相談しておくと安心です。
供養の形は一つではないので、今のあなたたちの暮らしに合ったやり方で進めてみてくださいね。
十三回忌 お墓参りだけで大丈夫でしょうか
今はお墓参りだけで済ませるご家庭も増えていますので問題ありません。
十三回忌は亡くなって12年目の大きな節目。でも、親族が集まりづらかったり、ライフスタイルが変わっていたりすることも多いんですよね。
例えばですが、命日に家族だけでお墓を訪れて、お花や好物を供えて静かに手を合わせるだけでも充分です。
お寺に相談して、読経をお願いすることもできますし、自宅で故人の写真に向かって手を合わせるという形も自然です。
もちろん、親戚に簡単にお知らせしておくことで、「あれ?今年は法要ないの?」といった心配も避けられますよ。
七回忌はやるべきかどうかの判断基準
結論から言えば、やるかどうかは家庭の事情次第です。迷ったときは、
などを考えると方向性が見えてきますね。
近年では、お墓参りだけにする人も増えていて、必ずしも法要を大きく行う必要はありません。
例えば、
という選択をする人もいます。
大切なのは、正解を探すことではなく、今の家族に合った形を選ぶことです。親戚やお寺と話し合って決めると、スムーズに進められますよ。
まとめ:七回忌の供養方法は柔軟で大丈夫
七回忌の供養方法に決まった形はありません。昔と違って今は、家族の事情や気持ちを優先して、柔軟に考える人が増えていますよ。
例えば、お坊さんを呼ばずにお墓参りだけで済ませたり、自宅で写真を見ながら手を合わせるだけでも、しっかり供養になります。

形式よりも、どう偲びたいかの気持ちが大事なんですね。
それでも、少しでも迷いがあるなら、お寺に相談してみましょう。信頼できる方に話を聞いてもらうだけでも安心できますし、ちょっとしたアドバイスで決めやすくなりますよ。
七回忌はあくまで故人への想いを形にする節目です。無理のない範囲で、自分たちに合った供養ができれば、それで十分だと思いますよ。