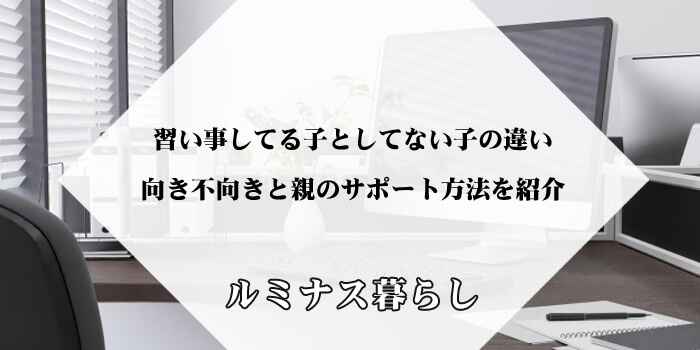「習い事をしている子と、していない子ってどっちがいいの?」と迷ったことはありませんか?
習い事はスキルや自己管理能力を伸ばす良い機会ですが、一方で自由な時間を持つことの大切さもよく言われます。
しかし「習い事をしないと成長できないのでは?」と不安になったり、「やらせすぎて子どもの負担にならないか?」と悩むこともあるでしょう。

結論として、習い事をしている子にも習い事をしていない子にも、それぞれ違ったメリットがあります。
この記事では、習い事をしている子としていない子の違いや、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
また、習い事の選び方や、ストレスなく続けるためのポイント、自由時間とのバランスの取り方についても紹介します。
「子どもに習い事をさせるべきか?」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
習い事してる子としてない子の違いとは?
習い事をしている子のメリット
結論から言うと、以下の3つです。
- 社会性が身につく
- 目標に向かって努力する力がつく
- 時間管理が上手くなる
このあたりが大きいですね。ただ習い事さえやっていれば、これらが身につくというわけではないので、そこは要注意です。
とはいえ、やらないよりは確実にメリットが多いので、順番に解説していきます。
①:人との関わり方が自然と身につく
習い事をすると、先生やコーチの指導を受けながら、他の子と一緒に学ぶ機会が増えます。
例えば、サッカーやバレエなどのグループレッスンなら、協力することが前提です。
そこで
が育ちますね。
一方で、個人競技やマンツーマンのレッスンでも、先生とやり取りする中で「自分の考えを伝える力」が鍛えられます。

これは、学校だけではなかなか学べない経験だったりしますね。
②:目標を持って取り組む姿勢が養われる
習い事には、明確な目標があることが多いです。
こういった目標があると、そこに向かって頑張る力が自然とついてきます。
さらに、目標を達成できれば「やればできる」という自信につながるし、もし失敗したとしても「次こそは」と挑戦する力が身につきます。
子どもの頃からこの感覚を持っていると、勉強や将来の仕事でも努力するのが当たり前になりやすいです。
③:時間の管理が自然とできる
習い事をしていると「今日は○時からレッスンだから、その前に宿題を終わらせよう」といった考え方ができるようになります。
これ、大人になるとめちゃくちゃ大事なスキルですよね。

例えば、社会人になると「仕事の締め切りまでに、この作業を終わらせる」といったスケジュール管理が必要になるわけですが、習い事を通じて自然と身につけておけば、後々ラクになります。
あと習い事と遊びのバランスを、考えるようになるのも大きいです。
遊びたい気持ちもあるけど、習い事も大事。
こういう葛藤の中で「どうすればうまく両立できるか?」を考えながら行動する習慣がつくので、結果的に時間を上手く使えるようになりますよ。
習い事をしていない子のメリット
「習い事はやった方がいい」とよく言われますが、本当にそうなのでしょうか?
もちろん、習い事には良い面がたくさんあります。でも、習い事をしていないからといって、成長の機会が減るわけではありません。
むしろ、自由な時間を持つことで得られるメリットも大きいです。
①:習い事がない分、自由な時間をたっぷり使える
まず、最大のメリットは時間の自由度が高いことです。
習い事がないと、学校が終わったあとや休日に自分がやりたいことにじっくり取り組めます。
例えば、以下のようなことができます。
「時間があるからこそ、自分の好きなことを追求できる」
これって、大人になってからも意外と大事な能力だったりします。
②:家族との時間が増えて、親子の会話が深まる
習い事をしていないと、その分家族と一緒に過ごす時間が増えるのも大きなポイント。
特に、習い事のスケジュールに縛られないから、夕飯の時間も家族そろってゆっくり食べられることが多いです。

たわいもない会話をしながら、「今日学校でこんなことがあったよ」と子どもが話してくれる。
これが、親子の信頼関係を深めるきっかけになったりするんですよね。
実際「習い事ばかりで忙しくなったら、子どもと話す時間が減った…」という家庭もあります。
子どもが小さいうちは、一緒に過ごせる時間が貴重なので、そういう意味では習い事をしない選択もアリだと思います。
③:友達と好きなだけ遊べるから、社会性も身につく
習い事をしていないと、放課後に友達と遊ぶ時間がしっかり取れるのもメリットのひとつ。
特に小学生くらいの時期って、友達との遊びを通して「ルールを守る」「意見を言い合う」といった社会性が育ちます。
例えば、公園で鬼ごっこをするだけでも、
こんな経験を、遊びの中で自然と身につけていくんですよね。
だから「習い事をしていない=社会性が育たない」というわけではなく、むしろ自由な遊びの中で学べることも多いんです。
スキルの習得における違い
「習い事をしたほうがスキルは伸びる」と思いがちですが、実はそうとも限りません。
スキルの習得方法は、大きく分けると「計画的に学ぶ」か「自然に身につける」かの2つです。
どちらが正解かは、子どもの性格や環境次第になります。それぞれの違いをサクッと解説していきます。
習い事をしている子は、計画的にスキルを伸ばす
習い事をしている子の強みは「体系的に学べること」です。
例えば、スイミングなら級ごとにステップアップできるし、ピアノなら楽譜の読み方から演奏技術まで、順序立てて学べますね。

さらに「指導者がいる」というのも大きいです。
わからないことがあれば、すぐに教えてもらえるので、最短ルートでスキルを習得できるというわけです。
もう一つのメリットは、継続しやすい環境があることあります。
毎週決まった時間にレッスンがあるので、やる気がない日でも続けられるのが強みです。
これが、習い事の最大のメリットかもしれませんね。
習い事をしていない子は、自分のペースで学ぶ
一方で、習い事をしない子は「自分の興味に合わせて自由に学ぶ」というスタイルです。
例えば、公園で遊んでいるうちに運動能力が上がったり、家で工作をしているうちに創造力が伸びたりします。
この方法の強みは、好きなことをトコトンやれること。
誰かに教えられるわけではないので、
といった自主性も育ちやすいですね。
ただし、スキルの習得スピードは個人差が大きいです。
ピアノや英会話のように、専門的な知識が必要なものは独学では限界があります。

一定のレベルまで伸ばしたいなら、習い事を検討したほうがいいケースもありますね。
社会性とコミュニケーション能力の差
「習い事をした方が社交的になる」
「いや、自由な環境のほうが自然なコミュニケーションが身につく」

どちらの意見も聞くけれど、実際のところどうなのでしょうか?
結論を言うと、どちらにもメリットがあります。
ただ、習い事をしている子とそうでない子では、社会性やコミュニケーションの伸び方が違います。
それぞれの特徴をざっくりまとめてみました。
習い事をしている子は「計画的にコミュ力を伸ばせる」
習い事をしている子の強みは、人との関わりがルール化されていることです。
例えば、スポーツなら「チームで動く」「コーチの指示を聞く」が基本になるし、ピアノや英会話でも「先生とやりとりする機会」が増えます。
つまり、人と協力したり、目上の人と話す経験が積みやすいということ。
また、発表会や試合といった「人前に立つ機会」も多いので、
こういったスキルが自然と身につくのも、習い事ならではのメリットですね。
習い事をしていない子は「自由な環境でコミュ力を伸ばす」
じゃあ、習い事をしない子はどうか?
実は、自由な環境だからこそ学べるコミュ力もあります。
例えば、公園で遊ぶとき、
こんな経験を繰り返すことで、「自分で考えて人と関わる力」が育ちやすいです。
また、親とじっくり話す時間が多いのもポイント。
習い事で忙しくなると、親と話す時間が減ることもあるけれど、習い事をしていない場合は、日常の会話の中で「自分の意見を伝える力」が伸びることもありますよ。
自己管理能力と自主性の成長
習い事の有無によって、自己管理能力や自主性の育ち方に違いが出ることがあります。
どのような環境で過ごすかによって、子ども自身が「自分で考えて動く」経験をどの程度できるかが変わるためです。
習い事をしている子は「計画的に動けるようになる」
習い事をしていると「決められた時間に動く習慣」がつきます。
「例えば、スイミングなら毎週○曜日の○時からレッスンがある」
このスケジュールに合わせて「体調管理」「宿題との両立」「練習時間の確保」などを考えるようになります。
また、ピアノや空手のように昇級試験や発表会がある習い事なら、「○月までにこのレベルに達する」みたいな目標設定も必要になってきますね。
結果的に、
このあたりが、習い事をしている子の強みです。
習い事をしていない子は「自由な環境で自主性を伸ばす」
一方で、習い事をしていない子の強みは「自由な時間を自分でどう使うか考える機会が多い」ことです。
例えば、
誰かに決められたことをこなすのではなく、
こういった経験を積みやすいのが特徴ですね。
ただ、スケジュールが決まっていない分「ダラダラ過ごしがちになる」こともあります。
親が適度にサポートするのがポイントですね。
習い事にかかるコスト|経済的&時間的負担のリアル
結論として、習い事をするかどうかは、家庭の状況次第です。
家計にどれくらいの余裕があるか、親がどこまで時間を割けるか、このバランスを考えながら決めるのが大事です。
習い事をしていると以下の2つがかかります。
まず、習い事をしていると、経済的な負担はそれなりにあります。
例えば、ピアノを習っている場合、発表会があるたびに衣装代や参加費がかかるし、スイミングなら進級テストごとに受験料が必要だったりします。
また、送迎の負担も大きいですよね。

習い事が週2回以上あると「仕事終わりに急いで迎えに行く」「夕飯の準備がバタバタになる」なんてこともザラ。
さらに兄弟がいる場合は、それぞれの習い事のスケジュール管理が超大変だったりします。
じゃあ、習い事をしないとどうなるか?
実際、「習い事にお金をかけるより、家族で旅行に行きたい」という家庭もありますよね。
また、自由な時間が増えるので、子どもが自分の好きなことを探求しやすくなるのもメリットの一つです。
習い事してる子としてない子、それぞれの選び方&続け方のポイント
子どもに合った習い事の選び方
習い事を始めるなら、子どもが楽しみながら続けられるものを選ぶことが大切です。
無理に親が決めてしまうと、子どもが興味を持てずに途中で嫌になってしまうこともあるため、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。
①:子どもの興味や性格を見極める
「せっかくだから役立つ習い事を…」と思っても、子どもが興味を持たなければ続きません。
例えば、「公園でずっと走り回っている」ならスポーツ系が合うし、「お絵かきやブロック遊びに没頭する」なら創作系の習い事が向いているかもしれませんね。
まずは、普段の遊びや興味のあることを観察することが大事です。
②:体験レッスンで「合うかどうか」チェック
「良さそう!」と思っても、実際に通わせてみると合わないこともあります。
そこでおすすめなのが、体験レッスンや見学です。
例えば、ピアノをやらせたくても、「音楽が好きだけど、じっと座るのが苦手」なタイプなら、リトミックの方が向いているかもしれません。
体験レッスンを受けることで、子ども自身が「楽しい!」と感じられるかを確認できます。
③:親の負担が大きくなりすぎないか?
習い事は子どもだけでなく、親の負担も重要なポイントです。
例えば、週3回の習い事があると、親の送迎スケジュールがカツカツに…。
また、月謝だけでなく「発表会・試合・ユニフォーム代」など、意外な出費があることもあります。
家庭のリズムを考えながら、無理なく続けられるかどうかもチェックしておきましょう。
習い事はいつ始める?ベストなタイミング
習い事を始める時期は、子どもによって違いますが、無理に早く始める必要はありません。
大切なのは、子どもが興味を持ち、楽しく学べるタイミングを見極めることです。
3歳〜4歳|遊び感覚でOK
この時期は、楽しく体を動かしたり、自然に学べる習い事が向いています。
「小さいうちからやらせたほうがいい」と思われがちですが、正直、無理に始める必要はありません。
子どもが楽しめているかどうかが一番大事ですよ。
5歳〜6歳|集中力がつき始める時期
この頃になると、少しずつ「じっくり取り組む力」がついてきます。
ただし「向いているかどうか」は個人差あります。
例えば「ピアノを始めたけど、じっと座っていられない…」なんてことも普通にあります。
いつ始めても上達スピードは変わる
「早く始めたほうが上達する?」
そう思うかもしれませんが、実はそんなことはありません。
例えば、ピアノを5歳から習った子と、8歳から始めた子。同じ練習時間をこなしていれば、最終的な上達スピードはそこまで変わりません。
要するに、
この2つが揃っているタイミングが、その子にとってのベストなスタートです。
習い事がストレスにならないための対策
習い事は、子どもの成長に良い影響を与えるものですが、無理に続けると逆効果になることもあります。
「なんで行きたくないのか?」をしっかり見極めて、適切な対応をしていきましょう。
① まずは、子どもの本音を聞こう
習い事を嫌がる理由は「なんとなく」ではなく、必ず原因があるものです。
こんなふうに、ちょっとしたことで「行きたくない」と感じることはよくあります。
まずは「どうして行きたくないの?」と優しく聞いてみましょう。
② スケジュール、詰め込みすぎてない?
これ、意外と多いパターンです。大人でも予定が詰まりすぎると疲れるように、子どもも同じです。
「週に何回なら無理なく続けられるか?」
「もっと自由時間が必要か?」
この辺りを見直すだけで、子どもの負担がグッと減りますよ。
③ 小さな目標を決めると、やる気アップ!
「なんとなく通ってるけど、楽しくない…」
そんなときは、目標を決めるとモチベーションが上がりやすいです。
ゴールが見えると、頑張る意味がわかって楽しくなることもあります。
④ 最悪、辞めてもOK
「一度始めたら、辞めるのはダメ!」…なんてことは、全くありません。
こういう方法もあります。
「無理に続けさせる」より、「どうしたら子どもが楽しく学べるか?」を大切にしていきましょう。
習い事は「続けること」よりも「楽しく学べること」が大切です。
もしストレスになっているなら、無理せず見直してみるのもアリですよ。
習い事、いつやめる?「判断基準」をチェック!
習い事を始めるときは「続けてほしい」と思うものですが、続けることがすべて正解とは限りません。
子どもの様子を見ながら、適切なタイミングを見極めることが大切です。
① 毎回イヤがるなら、要注意!
こんなサインが続いていませんか?
子どもが「もう嫌だ」と感じているなら、無理に続けさせても逆効果です。
一時的な気分のムラなら様子を見るのもアリですが、長期間続くなら見直しを考えましょう。
② 習い事の環境が合ってる?
こうした要因でストレスを感じている場合、習い事が「成長の場」ではなく、「苦痛の場」になっている可能性もあります。
無理に続けるよりも、別の教室や別の習い事を考えるのもアリです。
③ 生活リズム、崩れてない?
習い事は「成長のためのもの」ですが、生活に悪影響が出るようなら、ちょっと考え直すべきかもしれません。
「子どもにとって、習い事が今の生活に本当に必要か?」
スケジュールを見直して、負担が大きくなりすぎていないかチェックしてみましょう。
④ 「やり切る経験」をさせるのもアリ
すぐに辞めるのはよくない」と感じるなら、目標を決めて区切りをつけるのもアリです。
こうすることで、途中で投げ出さない力も育ちます。
結局のところ、習い事は続けることが大事なのではなく「学びがあるかどうか」が重要です。
もし続ける意味がなくなっているなら、無理をせずに「やめる決断」も選択肢のひとつです。
習い事のサポート、親の役割はどこまで?
子どもにとって習い事は大切な経験の場。
でも、親のサポート次第で、「楽しい学び」になるか「プレッシャー」になるかが変わってきます。
① 「やらせる」より「応援する」が大事
親として気になるポイントですが、まず大事なのは、子ども自身が楽しめているかですね。
無理に「頑張らせる」より、「楽しんでるね」「続けててすごいね」と声をかけるほうが、やる気は続きやすいですよ。
② ちょっとした関わりでモチベUP!
忙しくて時間が取れなくても、「今日のレッスンどうだった?」と聞くだけでOKです。
それだけで関心を持ってくれてると感じ、やる気につながります。
③ 親の負担、無理しすぎてない?
習い事って、親の負担も意外と大きいですよね。
でも、親が無理をしすぎると、子どもにも影響が出ることもあります。
「家庭の負担が大きすぎないか?」と一度、バランスを見直してみるのも大切ですよ。
習い事は、子どもが楽しみながら成長するためのもの。
親がサポートを「義務」に感じるのではなく、一緒に楽しむ姿勢が、習い事をより充実したものにしてくれます。
習い事 vs 自由時間|ベストなバランスの見つけ方
習い事は成長のチャンスです。
でも、そればかりになると子どもが疲れてしまいます。
ポイントは「習い事」と「自由時間」のバランスを取ることです。
無理のないスケジュールを組むことで、子どもものびのび成長できますよ。
① 習い事は週に何回が理想?
まず、週にどれくらい習い事を入れるかを考えることが大切です。
習い事が多くなると、学校の宿題や遊ぶ時間が圧迫されることもあります。
「最近ちょっと疲れてるかも?」と思ったら、習い事の回数を見直すのもアリです。
② 習い事の組み合わせ、ちゃんと考えてる?
例えば、サッカー&ダンスの組み合わせだと、体を動かす負担が大きくなります。
一方で、ピアノ&書道のように集中力を使うものばかりだと、疲れがたまりやすいです。
習い事の種類のバランスを取るだけで、子どもの負担をグッと減らせますよ。
③ 自由時間の「質」も大事
自由時間の過ごし方も意識しておくと、バランスが取りやすくなります。
子どもによっては、何も予定がないと退屈してしまうことも。
自由時間があることで、自分の好きなことを見つけたり、創造的な遊びをする機会になりますよ。
例えば、
習い事にはない自由な学びができるのが、自由時間の良さです。
予定を詰めすぎず、子どもが自由に楽しめる時間をしっかり確保するのも大事ですね。
習い事してる子としてない子、それぞれの選択を大切に
というわけで、最後にまとめます。
習い事をしている子には、社会性や自己管理能力が伸びやすいメリットがあります。
一方で、習い事をしていない子は、自由な時間の中で自主性や創造力を育てやすい良さがあります。
どちらが正解かはなく、大切なのは「その子に合った選択ができているか」ということ。

「周りがやってるから」「何か習わせなきゃ」と焦る必要はありません。
習い事をしているからといって、すべてがプラスに働くわけではないし、していないからといって、成長の機会が失われるわけでもありません。
習い事をする・しないに関わらず、子どもが「楽しい」と思える環境を作ることが、親にできる一番のサポートかもしれませんね。